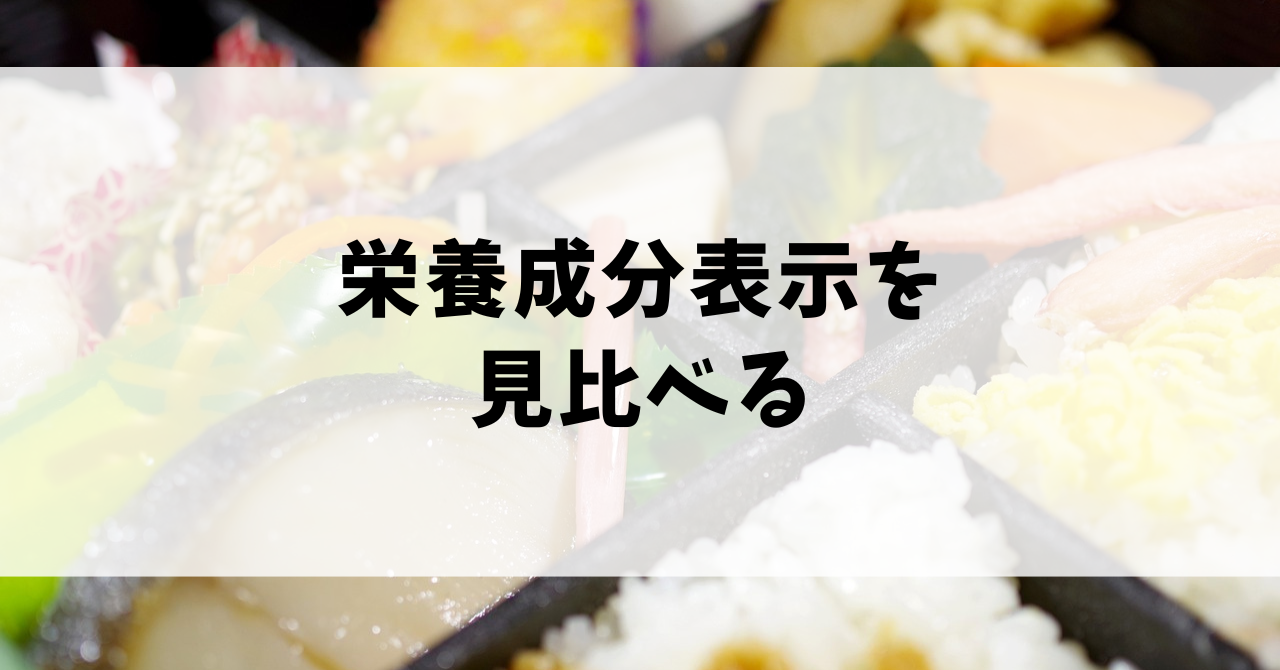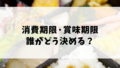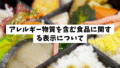スーパーやコンビニで、食品パッケージに記載されている栄養成分表示をチェックして見比べたことはありますか?日々の食品選びを賢くするために、栄養成分表示の見方と活用方法を紹介します。
栄養成分表示とは?
食品に含まれるエネルギー(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5つの主要成分の量を示したものです。消費者が適切な食品を選択できるよう、加工食品への表示が義務化されています。
栄養成分表示を読み解く2つのポイント
1.含有量と単位を確認する
商品によって 「100gあたり」「大さじ1杯(15ml)あたり」「1個(150g)あたり」 など、異なる単位で表記されています。
適切に比較するためには、同じ単位に換算して考えることが重要です。
2つのヨーグルトのカロリーを比較してみましょう。
<具体例>
ヨーグルトAとBを比較する場合
ヨーグルトA:100gあたり 70kcal
ヨーグルトB:1個(70g)あたり 60kcal
このままでは単位が異なるため、ヨーグルトAのカロリーを70gあたりに換算します。
計算式
70×70/100 = 49kcal
比較結果
ヨーグルトA(70gあたり)49kcal
ヨーグルトB(70gあたり)60kcal
→ ヨーグルトAの方が低カロリーであることが分かります。
2. 栄養素の働きを理解する
| 栄養素 | 働き |
| エネルギー(カロリー) | 脳や筋肉活動のエネルギー源 |
| たんぱく質 | 筋肉、内臓、皮膚の材料となるエネルギー源 |
| 脂質 | 細胞やホルモンの材料にもなるエネルギー源 |
| 炭水化物 | 脳や体の主要なエネルギー源 |
| 食塩相当量 | ナトリウム量を食塩量に換算したもの |
例:運動をする人はたんぱく質を多めに、ダイエット中の人は脂質やカロリーを控えめにするなど、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことができます。
栄養成分表示を活用するメリット
1. 健康管理がしやすい – 自分の食生活を可視化できる。
2. ダイエットに役立つ – 適切なカロリーや脂質管理ができる。
3. 生活習慣病を予防できる – 塩分や糖質を意識することでリスクを軽減。
まとめ
栄養成分表示の単位と含有量をチェックすることで、複数の中から賢く食品選ぶことができます。
早速、スーパーやコンビニで栄養成分表示をチェックしてみましょう。