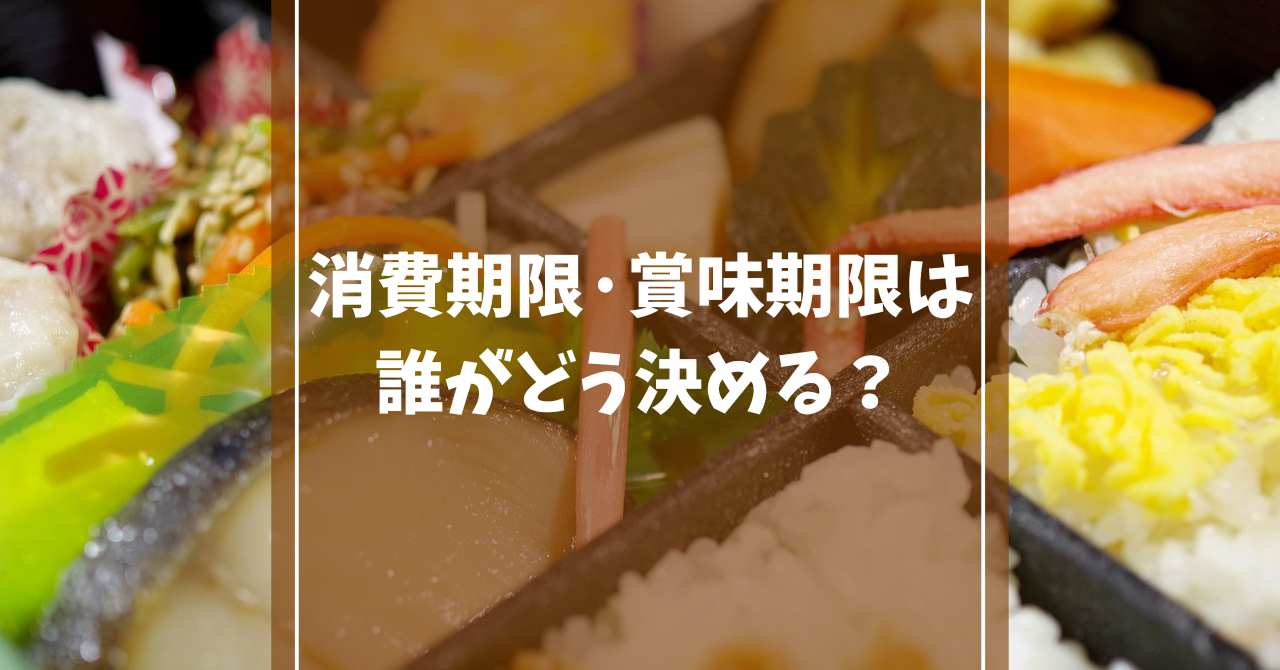
期限が切れても食べられたけど、パッケージの期限に根拠はあるのでしょうか?
「今まで問題ないからこのくらいだろう」といった経験則で決められているのでしょうか?
消費期限・賞味期限は誰がどのように決めているのか、解説していきます。
そもそも消費期限・賞味期限とは?
【消費期限】
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴
い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日
対象食品:弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなどの劣化が早い食品
【賞味期限】
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分
に可能であると認められる期限を示す年月日
ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする
対象食品:スナック菓子、缶詰、カップ麺、ペットボトル飲料、調味料などの劣化が遅い食品
| 項目 | 消費期限 | 賞味期限 |
|---|---|---|
| 対象食品 | 劣化が早い食品 | 劣化が遅い食品 |
| 設定基準 | 安全に食べられる期限=安全性重視 | おいしく食べられる期限=品質重視 |
| 期限を過ぎた場合 | 食中毒の危険がある | 風味や食感が落ちる |
消費期限・賞味期限の設定方法
メーカー、卸、スーパー、コンビニエンスストア、飲食店などの食品関連事業者が、根拠に基づき期限を設定しています。
根拠となる以下の試験が行われています。
- 理化学試験(pH、糖度、水分活性、酸度、酸化度など)
- 微生物試験(食中毒菌の有無、増殖状況など)
- 官能試験(色、香り、食感など)
試験結果がそのまま消費期限・賞味期限期限となるのではなく、試験結果に「安全係数(1未満)」をかけて実際の期限よりも短い期限が設定されます。
例:菓子の試験結果
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 |
| 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
合格した期間 × 安全係数(1未満) = 3日 × 0.8 ≒ 2日
まとめ
食品事業者の試験結果に安全係数(1未満)をかけたものが期限となり、根拠に基づいて設定されます。